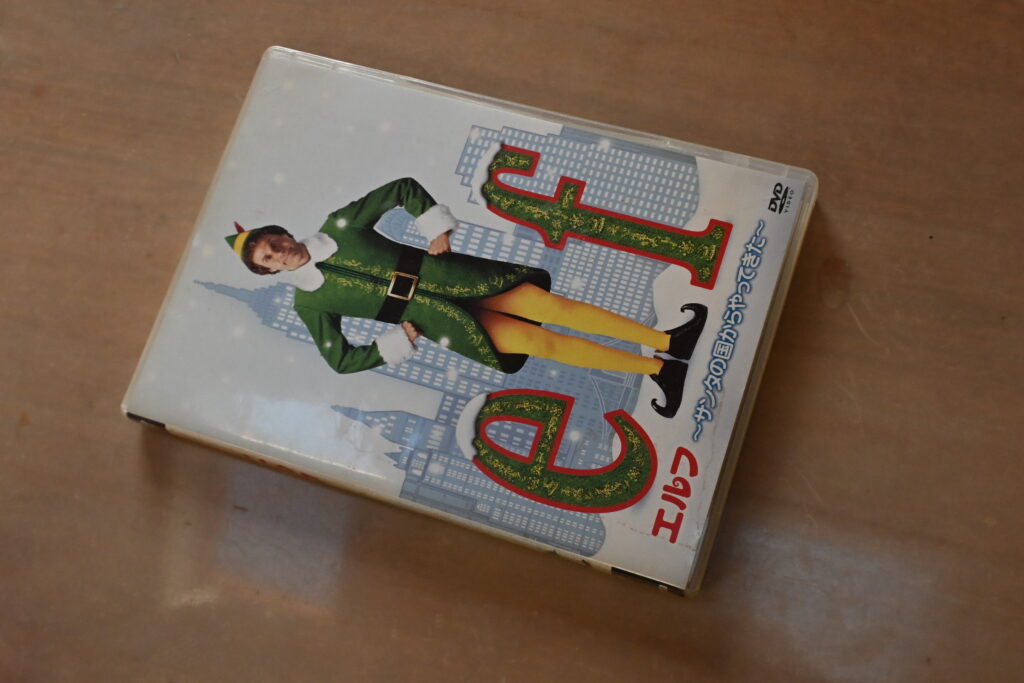Youtube クリスマスの動画に足りないもの
このところYoutubeでヨーロッパのクリスマス・マーケットをめぐる動画をよく見る。
母がクリスチャンだった僕にとって、クリスマスは今も欠かせない年中行事だ。だが娘たちが成人して「子供」が存在しない我が家では、今一つ気分が盛り上がらない。そこでYoutubeの力を借りよう、というわけだ。
Youtubeには実に数多くのクリスマス関連動画があって、それなりに楽しい。だが実を言うと、どの動画を見ても何かが足りない気がする。動画ではかわいらしいクリスマスの小物やおいしそうな屋台グルメが紹介され、ヨーロッパの美しい街並みを見ることもできる。なのに今一つ、心に染み入ってこない。なぜだろうか。
我が家には20年ほど前に録画したBSフジの特番、「世界の街からメリークリスマス」と、NHKが放送した国際共同制作番組「クリスマスツリー物語」のディスクがあって、毎年この時期になると家族で視聴する。
「世界の街からメリークリスマス」は世界各国の街角から楽しげなクリスマスの様子を、インタビューを交えながらレポートしていて、各地で開かれるクリスマス・マーケットもふんだんに紹介されている。「クリスマスツリー物語」はある貴族一家のクリスマスにまつわるドラマを軸に、クリスマスツリーを飾る習慣がいかにして生まれ、どのように世界中に広まったのかを、アカデミックなドキュメンタリーで紹介するという凝った作りだ。この番組は今でもYoutubeで見ることができる。
不思議なことにこの二つの番組はなぜか抵抗なく心に入り込み、いまだに僕を素敵な気分にさせてくれる。いったい何が違うのだろうか。
考えてみると、Youtubeで見た動画の多くは場面を説明するナレーションが入っていない。時たま字幕が入るだけだ。撮影者が周囲の人々と会話することもない。一方TV番組のほうはどちらもナレーションが入り、関係者へのインタビューも含まれているので、視聴者と制作側のあいだにある種の「対話」を感じる。加えて「世界の街からメリークリスマス」では、通行人の母国語によるクリスマスのあいさつや即興の合唱など、現場の楽しさがストレートに伝わる工夫も満載だ。
もう一つ気づいたのがBGM。TV番組のほうはどちらも古典的な讃美歌からスタンダード、果ては現代的なポップスまで、数多くのクリスマスにまつわる曲が使われ、番組の雰囲気づくりに大いに役立っている。Youtubeでは一人のチャンネル制作者が使うのはせいぜい1~2曲で、シリーズものでは一つの曲が使いまわされている事もある。さらに意外なことに、動画で見る限りクリスマス・マーケットでは音楽が流されていないことが多く、BGMの無い場面では延々と雑踏の騒めきが聞こえるだけだ。人出はそれなりにあるのに、なんだか寂しげに見える。
TV局が番組を制作する場合、それなりの予算が組まれるから、「世界の街からメリークリスマス」や「クリスマスツリー物語」のように複数のナレーターや声優をキャスティングし、数多くの曲を使うことができる。だが予算が限られる個人や少人数のグループが制作するYoutubeではそうはいかない。そこに比べること自体が酷なレベルの、演出上の差が生まれる。
Youtubeのクリスマスマーケットに関する動画は余計な演出がない分、現実感や臨場感ではTVに勝っている。まるで自分が現場を歩いているような感覚だ。だがBGMも語る相手もなく、一人雑踏の中を散策するかのような場面では、リアルであるがゆえの疎外感を感じてしまう。音楽のないクリスマス・マーケットのシーンで感じた寂寥感は、おそらくそれが原因だろう。
クリスマスは一種のファンタジーだ。それは非日常でもある。だからこそ、見るものを楽しませる意図的な演出が必要になる。僕たちが子供だったころ、大人たちがそうしてくれたように。僕が見たYoutube動画に足りなかったものは、まさしくそれだろう。