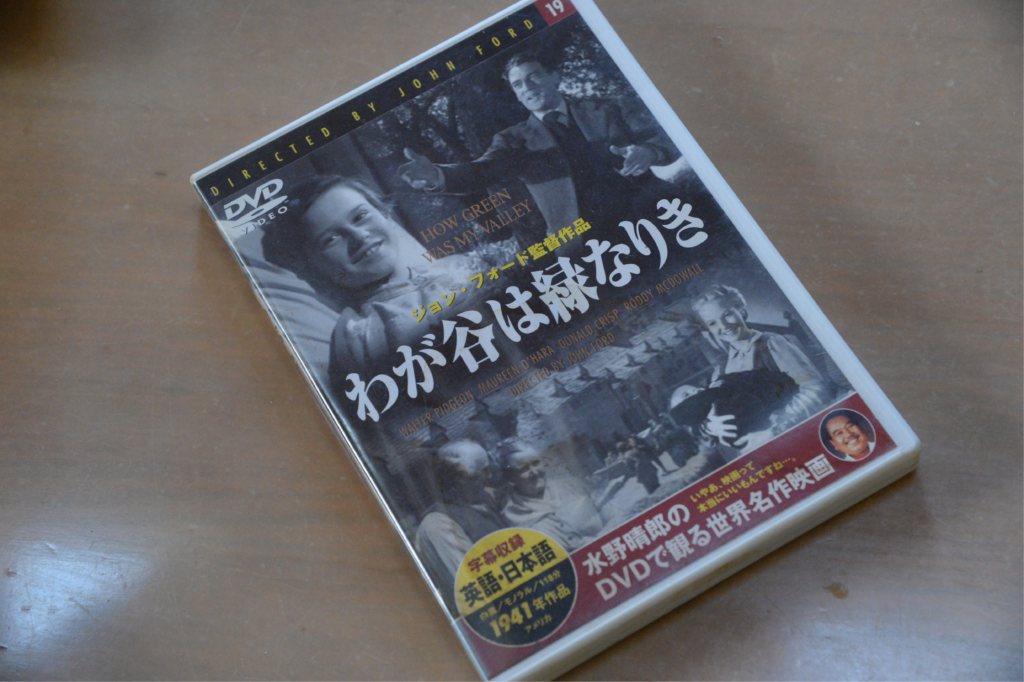町のブラックジャック
数年前の夏、僕はブラック・ジャックに出会った。といっても、べつに黒いマントは着ていなかったし、顔の半分の色が違ってもいなかった。メスを忍ばせていたりもしなかったな。そもそも道具らしい道具は使わなかった。
その時僕は、ケガをしたなじみの(?)野良ネコを何とかしてやろうと、動物病院に連れて行った。そしてその治療中、慣れない環境におびえたそのネコが、僕の左薬指を本気で噛んだのだ。かなりざっくりいったので血がしばらく止まらなかった。ぼくの見立てでは3~4針縫うキズだった。獣医さんでキズ絆をもらったが、止血するのに5枚ぐらいは使っただろうか。獣医師は法律上人間の治療はできないので、ネコをうちに連れ帰ったその足で、僕は緊急夜間の外科医を訪ねた。受付で「どうされましたか」と聞くので、僕は事の一部始終を説明した。そして最後に、 「何針か縫う様だと思います。」 と付け加えた。
しばらくして名前を呼ばれ、診察室に入ると、ちょっとロン毛の白髪の老医師がいた。ケガをした顛末を聞いた後、彼は僕に尋ねた。 「消毒はしてあるんだね?」 「いえ。ですがあれだけ出血すれば問題ないと思います。」 「ふむ。」 彼はヨードか何かの液体で傷口をあらためて消毒し、 「ちょっと痛いかもしれんよ?」 と言って、いきなり傷口を左右からつまみ、締め上げた。 「!」 びっくりしたが、特に痛みは感じなかった。そのまま1分足らずじっとしていた。すると医師がいきなり、 「ほら!テープ巻いて!もたもたしてんじゃない!テープ!」 これは医師から看護士への指示だ。老医師にあるまじき迫力。まるで罵倒しているようだ。 「は、はい!」 看護士は慌てて傷口をそれ専用らしいテープで巻き、これまた締め上げた。医師が、こんどは僕にむかって、 「痛くないかな?あまりきついと血が止まっちまうからね。」 「大丈夫なようです。」 「よし。明日また来て。キズを確認して消毒するから。」 「は、はい。」 えっ?終わり?つまんでテープを巻いただけなんだけど。でもまあ、縫うよりは時間はかからないな。抜糸の手間もないし。いやいや、そういう問題か?その後、看護士さんに 「結婚指輪はしばらく外しておいてください。もし化膿して腫れ上がると、外れなくなって指が壊死したり、指輪を切り取ることになったりするんで。」 などと恐ろしいことを言われ、テーピングの上から包帯を巻いてもらって(やっと治療してもらった気分になった)会計をして帰った。
昔教師をしていた経験上、どう見ても3針以上は縫うだろうと思っていた。(綺麗に治そうとするならもっとかな。)それがつまんで1分、テープを巻いて終わり。翌日も腫れはなく、包帯がキズ絆に変わった。格下げかーい!結局2週間ほどで、わかりにくい傷跡だけを残して治ってしまった。今ではその傷跡も、言わなきゃわからない程度である。近代医学とは何かが問われる出来事であった・・・?