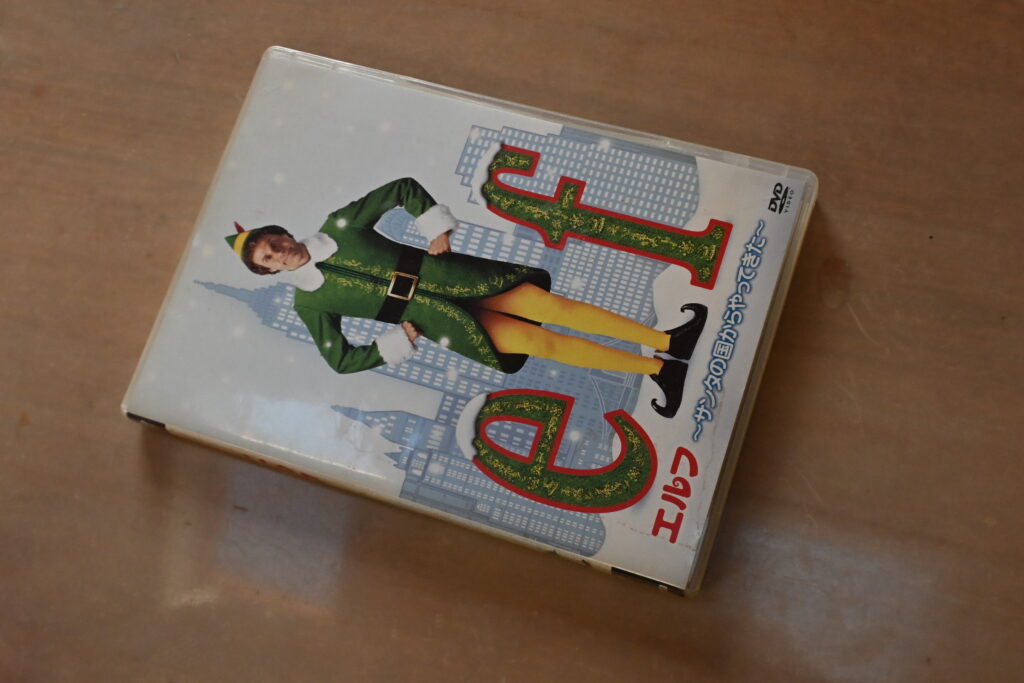ハリウッドタウン
前に一度書いたハリエット・ショックというミュージシャンのデビューアルバム、「ハリウッドタウン」。高校生だった頃、FMで一耳ぼれ(この表現、合ってる?)したものの、小遣い事情が厳しくて手に入れることは叶わず、以来一度も目にしたことがなかった。前回の記事ではアメリカ人の知り合いの尽力によって、何十年もの年月を超え、カリフォルニアのショップにあったデッドストックが奇跡的に手に入った顛末を書いた。
数日前に部屋の整理をしていたら、そのタイトル曲である「ハリウッドタウン」の歌詞(英文)が出てきた。これはイギリス人の知り合いが、ネットで見つけてプリントアウトしてくれたものだ。それというのも、僕が手に入れたアメリカ版には歌詞カードなんて入っていなかったから。
日本語訳も欲しくて、これまでに何回かネットで探してはみたものの、ハリエット・ショックは日本では超マイナーということもあって、いまだに見つかっていない。なぜ自分で訳さないのかって?実はハリエット・ショックは歌を作るかなりの名人(?)で、一時期は大学で詩の講座をもっていたぐらいの人なのだ。だから英詩特有の「韻を踏む」ことを重視していて、簡単には意味の通らない語呂合わせ的な文章がよく出てくる。その他にも聞いたこともないような言い回しが多く使われていて、まともな日本語として翻訳するには英詩への慣れが必要なのだ。もちろん今までに何回も日本語訳を試みたが、僕のつたない英語力ではどうにもならず、中途で投げ出した状態だった。
そんなある日、Youtubeでハリエット・ショックのミックスリストを見つけた。その中に「ハリウッドタウン」の英文の歌詞を表示しているものがあり、何気なくその動画を見ていて、あることに気づいた。僕の持っているプリントの歌詞と歌の内容が一部違っているではないか。
あらためてプリントをよく見ると、冒頭に「MANNFRED MAN」とある。今まで意識したこともなかったが、調べてみるとイギリスのバンドの名前だった。僕の持っているプリントは、この「マンフレッド・マン」とやらがカバーしたバージョンの歌詞らしく、一部が改変されていた。なんということでせう、今まで気づかなかったとは…!すぐさまYoutubeの歌詞をプリントに書き写し、オリジナルを完成させた。今後それをもとに、あらためて日本語訳に挑戦してみようと思う。
ところでこの韻律の問題だけれど、日本の歌ではあまり聞かない。でもラップが流行ってからはかなり意識されているようだ。例をあげると「~したい ~できない ~気分はハイ」これらは語尾の(アイ)という音が共通。簡単に言うとこんな感じ。海外の詩や歌詞ではこうした「韻を踏む」ことが重要な要素になっている。例えば「ハリウッドタウン」には「Stepping on stars and shining on cars」という一節があるが、前半と後半の語尾の音がほぼ同じだ。
かつて「サイモン&ガーファンクル」のポールサイモンは、韻律にとらわれると思うように詩が書けない、と葛藤したことがあって、その境遇を「キャシーの歌」という曲で吐露している。ハリエット・ショックはこのあたりを踏まえた作詞がずば抜けて上手かったのだろう。海外版ウィキペディアでは「大学で英語(!?)の学士号を取った」という記述があるぐらいだから、洋楽を聞きかじった程度の僕なんかが訳そうと思っても、そう簡単に太刀打ちできるわけがないのだ。