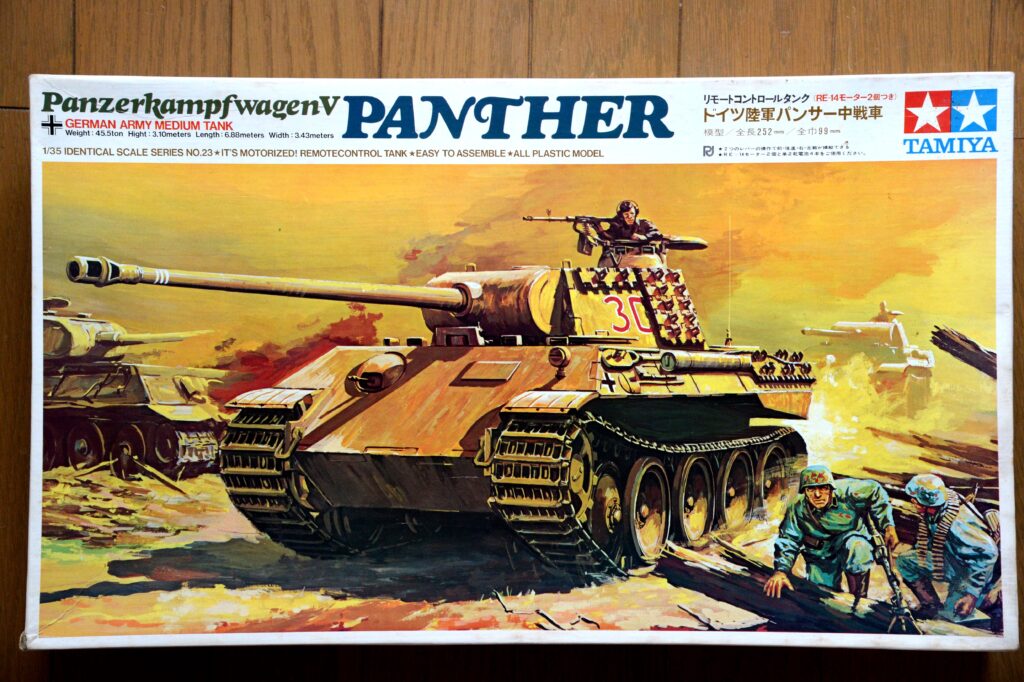結局、そうなるんだよ 前編
昨年の10月、ニコンのミラーレスカメラ、Zfが発売された。往年の名機、FM2に寄せたそのデザインが多少気になってはいたけど、その頃の僕はミラーレスカメラには全く興味がなかった。
僕は光学ファインダーの信奉者なので、現在はニコンDfを愛用している。ミラーレスカメラに搭載されている電子ビューファインダーは、そのファインダー象に違和感があって一向に馴染めない。だからZfが発売された時も、あれは僕が持つべきカメラじゃねえな、といった印象だった(同じくミラーレスのZfcを使ってはいるが、あれは僕の中では別枠で、「ちょっとおっきいけどいろいろと便利なコンパクトカメラ」といった位置づけだ)。
Zfは発売前から予約が殺到したらしい。一か月待ちは当たり前で、店頭のディスプレイも当初は実物大の写真ボードだけだった。半年ほどたってやっとディスプレイモデルが展示されるようになり、近場の家電量販店で何気なく手に取ってみたとき、僕はあることに気づいた。
以前Dfの記事の中で、そのデザインから想像するに、近々F3に似せたデジタル一眼が出てくるかもしれない、と書いたことがあるが、Zfを手にした時の感触は、なぜかF3にとてもよく似ていた。F3といえば僕が最も長く愛用したフィルムカメラで、当時の金属製カメラとしては珍しく、ボディにグリップ状の出っ張りがあった。よく見るとZfにも同じようなグリップがある。なるほど、それでか。
Zfのカタログには「FM2から着想を得た外観」と書かれているが、デザイナーが本当にFM2にこだわったのならこのグリップはなかったはずだ。そう考えると、確かにペンタ部(上部の三角形の張り出し)のデザインは違っているものの、全体的なフォルムはF3に似てなくもない。もしかしてこのカメラ、実質的には僕が予想していた「なんちゃってF3デジタル」なのではなかろうか。そう思った途端、急に興味がわいてきた。これはまずい。欲しくなったらどうしよう。
あらためてカタログデータを調べてみると、センサーはフルサイズでボディは金属製。いいね!…いやよくないぞ。この流れはよくない。だがファインダーが僕の嫌いな電子ビューであることは動かぬ事実だ。ところがここでなぜか突然、僕はジオン公国軍パイロット、ララァ・スン少尉の言葉を思い出した。「機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙」のなかで、彼女は確かこう言っていた。「人は変わっていくわ…私たちと同じように。」
さて、気持ちが前向きになったところで(!!!?)、新たな問題が。そう、予算の問題だ。以前Dfを購入したとき、僕は後先考えずに行動した。だがあの頃と今では状況が違う。どうする?いや、タクシーは呼ばなくていい。
実は今年、僕は長年にわたってため込んだカメラの断捨離を始めた。今までに4台のカメラを買い取り業者に売り払い、ちょっとした小遣い稼ぎをしてきたが、値段の折り合わなかったカメラがまだまだ残っている。これらを下に出せば、あるいは手持ちの予算でZfが手に入るかもしれない。幸い車で10分ほどのところに「カメラのキタムラ」がある。確か下取りもしていたはずだ。思えばここ10年ほど、「カメラ店」を訪れたことがない。久しぶりに専門店を覗くのも楽しいかもしれない。(つづく)